酒恋うる人

永遠の酒敵

大吟醸の初発売を称える
吟醸酒の市販
−中略−昭和47年1月に「大洋盛」が発売される。
「大洋盛」では製造課長の発売提案に全社あげて反対したが、課長の熱意に押されて20本だけビン詰めした。レッテルは社長が手書きしたものを使った。7、8本売れたところに10本まとまった注文が入り、レッテルを石版刷りに切りかえたという。同社の吟醸酒の買上げ名簿は、今日まで通し番号で保存されている。
 −中公新書「日本の酒づくり」P129−
−中公新書「日本の酒づくり」P129−
これは私の本の一節である。いま、吟醸酒はブームだ。その中でどれがいい酒か、どれが本流かを選ぶ目安に、蔵の吟醸酒の初売時期を参考にするとよい。
吟醸酒とは蔵の心意気である。精魂込めて酒を醸す。そしてその品質を世に問う。その心の披瀝が何時だったか。
初発売の歴史は、蔵の心意気を刻んでいるのである。

讃酒・わたしと越後流
遥か遠い白き神々の座、朝日連峰に源を発する清流三面川(みおもてがわ)は、村上の鮭たちの生命を育む母なる川であり、名酒「越後流」を醸す源泉でもある。鮭も酒も清冽な水が命で往古から鮭酒同源である。
この水と地元の酒造好適米・たかね錦を磨きに磨き、深々と降りしきる雪の蔵で 酒造に打ち込む蔵人の技術の冴え、恵まれた北越の自然と酒匠の心技が見事に融合し、創りだされた名作が大吟醸「越後流」である。
酒造に打ち込む蔵人の技術の冴え、恵まれた北越の自然と酒匠の心技が見事に融合し、創りだされた名作が大吟醸「越後流」である。
仕事の緊張から解放され、今宵も旬の佳肴と愛玩の酒盃で「越後流」を酌む。ほのかな薫をききながら、淡麗な味わいの酒格がわたしを魅了する。美酒を嗜み、器を愛でる至福のひととき、酌むほどに我が去来を想う。
「越後流」は、まさに酒の芸術品である。
※イヨボヤ会館=日本最初の鮭の博物館


酒王 大洋盛
大洋盛との出会いは、偶然である。
数年前、我が家もパソコンを導入し、インターネットを活用するようになった。そこで村上水軍関連のホームページを検索していたが、どなたも経験がおありであろう、自分の名前を検索してみた。すると「村上の大洋盛」が画面に現れたのだ。おそらく私の口は、数十秒間は開いていたに違いない。
『村上市の大洋盛とは・・・、出来すぎだ・・・』
もうそうなると矢も盾もたまらない。即、大洋酒造に便りを出し、数日後、本醸造大洋盛を発送していただいた。
封を開け、船徳利に注ぎ、燗をつけると、その芳香がたまらない。その時点で酒のうまさが伝わってくる。
ひとたび口に含めば、芳醇な世界に満ちあふれる。
喉を通過する一滴一滴が、細胞に染み込んでいく。
すると私の脳が、「はやく二杯目を飲め」と刺激する。
「これこそが自分の求めていた日本酒だ」
はなればなれの恋人とやっと巡り会えたような喜びであった。
世に村上水軍と言われる我らの先祖は、十四世紀末、信濃より瀬戸内に進出したものと伝わる。「村上という地名は、村上家と関連がある」とも耳にしたことがある。
遠い昔、先祖のもののふ達が行き来したであろう信濃や越後の山、川、野原の風景が、大洋盛を飲むたびに容易に想像出来るのだ。その香りや水本来のうまさに何故かなつかしさを感じるのは、大洋盛が私のDNAに語りかけているからなのだろう。このようなうまいお酒は、自分が知人や友人に勧めなければいけない衝動に駆られた。六本入りの箱から、一本、一本、また一本と消えていった。
気がつくと自分は一本しか空けていなかった。
惜しい気もあったが、後日『あのお酒すごくおいしかったよ。さすが新潟のお酒だね。二日半で空いちゃったよ。』と言われれば、自然、顔もほころび、また普及活動に熱が入ると言うものだ。飲ん兵衛をかたっぱしから唸らせるとは、私の日本酒番付けで、大洋盛は横綱である。
これからは「酒王」と冠し、呼ぶことにしよう。
乾杯! 酒王大洋盛
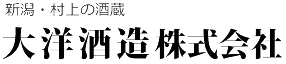
 クリックで拡大
クリックで拡大